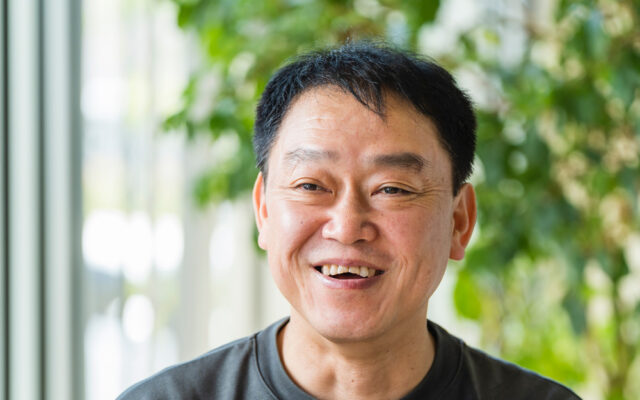警察OBが自らの経験や知見を活かし、
災害時に警察や自治体を支援したい。
―NPO法人災害時警友活動支援ネットワークについて簡単にご説明いただけますか。
竹内 次の大災害に備えるため、警察OB等の民間ボランティア会員が、自らの経験や知見を活かして、自発的に警察や自治体等の関係助言や支援を行うとともに、災害で得た教訓を伝承していこうというNPO法人です。
検視や身元確認の補助、行方不明者家族への対応、防犯パトロールやデマを打ち消すためのチラシの配布、被災情報の収集や連絡等といった活動によって、被災された方々はもちろん、その前段階として、警察や自治体などの関係機関を支援したいと考えています。
と言いますのも、私は平成23(2011)年3月11日の東日本大震災の時、宮城県警本部長という立場にあったんです。職員14名が殉職してしまい、それを防げなかったことが今も悔やまれてならないのですが、ここまでの事態になるとは想像できなかった。発災後、現場では本当に苦労しながら、全国の警察や自治体の支援を受けながら、何とか形にすることができましたが、実は、一部の宮城県警OBから「何か手伝えることはありませんか」と言う声が届いていたんです。しかし、余震が続き、津波注意報が出されている最中、万が一の時の補償の枠組みもないのに手伝っていただくことは難しい。断念せざるを得ないという経験がありました。
―さまざまな経験をお持ちの警察OBの方が支援に入ってくださったら、さぞ心強かっただろうと思います。
竹内 もともと、警察OBが支援とか助言ができないわけではありません。ただ、法人格を持ったほうが、被災地に人材を派遣するにしても、任意団体より受け入れてもらいやすいでしょうし、社会的な認知度も変わってくると思います。それでNPO法人を立ち上げたのです。相手方のニーズとこちらが提供できるシーズをマッチングすることで、現場のお役に立てる活動ができると思っています。
その一つがロジ支援です。他の府県から派遣されてくる地方自治体の職員とか警察の応援部隊とかに対して、例えば宿の手配とか、宿から現場まで行く足の確保とか、すごく細かい話ですが、営業しているコンビニの場所の確認とか、そういう支援を警察OBはできると思うんです。
ただ、うちの会員がボランティアとして手弁当で現地に行くとしても、交通費くらいは受け入れ側の自治体なり警察が支援してくれないかという思いはあります。そういう段取りを決めておくためにも、やはり事前に各自治体や警察と支援協定を結んでおく必要があるわけで、そのためにも法人格は必要ですね。

東日本大震災の時は宮城県警本部長として現場の指揮に当たった。左が竹内さん
災害時だけでなく、
訓練の段階から支援したい。
―会員には、東日本大震災の際に、多くのご遺体の検視や身元確認等の業務に従事した方が多いそうですね。
竹内 遺体安置所の設置・運営、ご遺族や行方不明者の対応は、本来は自治体の領域なのですが、そう簡単に物事は進まないというのが14年前の経験で、宮城県警はそういった業務を行いましたし、今後も警察は関わっていったほうがいいと個人的に思っています。
ご遺体が多数出た時に、そのご遺体を遺体安置所でどう扱うかということだけではなく、その前の段階で行方不明者が出るわけです。特に津波型の大災害、あるいは首都直下のような都心での大災害の場合、居住地や勤務地でないところで被災する人が出る。旅行者だったり、そこにはもちろんインバウンドの外国人もいます。大変悲しいことですが、たまたま被災して、そこで亡くなってしまうと、その方の身元をどうやって確認するか。身元確認は警察の仕事なのですが、その前段階である行方不明者の情報が、どこにどれだけ集まるかということが課題だと思います。
今は情報収集も主に自治体の領域とされていますが、例えばお遍路さんで行ったうちのおじいちゃんが津波でやられたらしいという問い合わせを高知や徳島の市町村に個別に電話しなければいけないのでしょうか。自治体や現役の警察もそこまで手が回らないということであれば、まさにそういう部分でお助けできるのではないかと思います。
―防犯対策も警察の得意とする分野ですね。
竹内 東日本大震災の時もそうですが、能登半島地震の被災地ではいまだに安全安心の問題があるんですね。例えば火事場泥棒的な人間が入り込んで、半壊になった家から貴重品を盗る。14年前はコンビニのATMから現金を持っていく事件も多発しました。被災された方からすれば、大変な目に遭ってすごく不安なところに、さらに追い打ちをかけるような犯罪が起こる。それを防止するのは主に警察の仕事ですが、自治体も防犯対策をやれる部分は結構あります。
例えば、青色の回転灯をつけた車が都内を走っていますね。あれは警察ではないのですが、防犯効果が高い。我々も、能登半島でやろうとしたんですが、実施するためにはいくつか手順があるので、なかなか進まない。でも、人手が足りないのであれば、そこをお手伝いできると思っています。
それから、デマが流れるわけですよ。意図的に流す悪質な人間もいるし、面白半分に流す人間もいますが、いずれにしても不安を煽るようなことをする輩が残念ながらいるわけです。それを打ち消すためには、実際に起こっている犯罪はこの程度ですよというビラを避難所に行って配ることが大切です。そんなお手伝いもできると思います。
また、今年8月に総合防災訓練が羽村市で行われ、うちの会員もオブザーバー的な形で参加しましたが、災害時にお手伝いするだけでなく、むしろ訓練の時や、訓練のプランニング時に、「こういう想定も入れたほうがいいのでは」といった助言もしていきたいです。
災害対応は警察だけでも、自治体だけでもやれるものではありません。その間をつなぐリエゾン(橋渡し)のような形で、お役に立ちたいと思います。

NPO法人災害時警友活動支援ネットワークの
代表理事として危機管理の要諦等を伝えている
東日本大震災の現場に居合わせたことは、
警察人生としてマイナスではなかった。
―警察庁に入ろうと思ったのは?
竹内 国家公務員になって、政府の仕事をしたいと思っていたんですね。採用試験に受かって各省庁を回っていた時、たまたま同期から「警察庁も行ってみたら」と言われたんです。試しに行ってみたら、私の思っていた警察のイメージと全然違ったんですよ。とてもフランクに接してくれて、警察は単に犯人を捕まえるだけでなく、現場を支えるために、法律を整備するとか、予算を取るとか、仕組みを作るとか、国家公務員としてやりがいがあると分かりました。
それで考え直したんですが、亡くなった父は金融機関だったので、勝手に大蔵省に行くと思っていたようなんです。ある時、「警察庁も考えてる」とポロっと言ったら、ものすごく反対された。私も天邪鬼なものですから、反対されると「いや、警察庁は実はこういう役所で……」となって、それで入庁させていただくことになりました。
でも一番の理由はそこで接してくださった方とのご縁ですね。
―思っていたような仕事はできたのですか。
竹内 平成3(1991)年の暴力団対策法制定時には立案チームに入って、その中の大事な部分を任され、最終的に法律になりました。自分が起案した条文が六法全書に掲載されるわけですから、達成感はありましたね。
警察庁の警察官というのはかなり特殊な職種で、前述のような霞ヶ関的な業務もありますし、まさに宮城県警時代がそうですが、組織のトップみたいな現場の仕事もある。その両方をやれるというのは魅力に感じていました。
ただ、その現場の仕事が、まさか東日本大震災という、それこそ想定外な場に居合わせることになるとは……。幸か不幸か、その時にそういう立場にあったという自分自身は変えようがありません。これも私の警察人生としては、決してマイナスではなかったと思っています。
―警察を辞めてから、警察謝恩伝道士という活動をされていますね。
竹内 私が勝手に名乗っている造語ですが、東日本大震災の時にお世話になった全国津々浦々の警察職員の皆さんなどに「ありがとうございました」という気持ちを伝えたかったんです。それで、自分が教訓として持っていることを次に繋げることで感謝に変えたいと、全国各地で講演を行ってきました。
能登半島地震でもそうだと思いますが、警察や政府は災害対応を記録し、膨大な報告書を作ります。それに基づいて、対策を練り、予算を投じていくという形でPDCAは回っていくわけですが、それを補足するのが口承ではないでしょうか。ある意味、紙の媒体やネット上で検索対処できるデータ以上に、対面でお伝えすることがすごく重要だと思っています。
災害対応の記録や、報告書に書かれないような細かいノウハウなどを資料化する、教訓を語り継ぐ、そういった側面的なお手伝いもできると思います。黒子というか縁の下の力持ちですが、より現場に近いところで実活動につなげていきたい。僭越な言い方ですが、お役に立てることがあるなら、もうちょっと頑張ってみようと思っています。

自らの教訓と感謝の気持ちを伝えたいと、全国各地の警察で講演を行っている

竹内 直人|たけうち なおと 1957年福井県生まれ。1981年東京大学法学部卒業後、警察庁に入庁。2009年10月から2011年10月まで宮城県警本部長を務め、東日本大震災に遭う。その後、外事情報部長、東北管区警察局長、警察大学校長を務め、2015年退官。退官後「警察謝恩伝道士」を名乗って震災の語り部活動を続ける。2023年9月警察退職者等による災害時の支援組織であるNPO法人災害時警友活動支援ネットワークを立ち上げ、同代表理事に就任。現在は第一生命保険株式会社公法人部に勤務