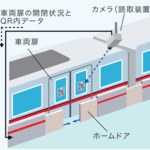震災後の復旧復興に携われるのは
男冥利に尽きる、幸せな人生。

石川県輪島市長 坂口茂さん
石川県輪島市に三男として生まれ育った。県外の大学を卒業後、民間企業に勤めていたが、両親が体調を崩したため地元へ戻る。輪島市役所の職員となり、地元の発展に関わりたいと様々なプロジェクトに参加した。2022年に輪島市長に就任。2024年に起こった能登半島地震の復旧復興に尽力している坂口茂輪島市長にお話を伺った。
家屋もインフラも震度7を想定して耐震化すべき
—能登半島地震が起きて1年3ヶ月余りが過ぎました。復旧の状況はいかがですか?
坂口 応急復旧ということで、とにかく道路を通すということがなされてきていますが、しっかりとした復旧はまだこれからです。まずは倒壊した建物を解体・撤去しないと次に進めません。今は一生懸命その作業に取り組んでいるところです。
ただ、解体する建物が親の名義だと、自分の持ち物だとしても相続が発生するので、関係する全員のハンコが揃わないと解体できない。実印が必要だといっても、地震で実印がどこにあるかわからないような状況ですから、そんなことは不可能ですし、裁判沙汰になることも予想されます。
最終的には環境省と法務省が、代表者がその責任を持つという書類を書いて手続きをすれば、権利者全員の同意がなくても、自治体判断で倒壊・焼失した家屋を解体・撤去できることになりました。二の足を踏む自治体が多かったですが、輪島市はそんなことは言ってられないと、12000棟を超える申請のうち約1500棟以上を、その方法で解体する予定です。
—地震が起きて、まず何をされたのですか。
坂口 とにかく庁舎に行かなければと、車を使える状況ではないので、歩いて近くの支所に向かいました。
途中には建物が倒れてその下敷きになって助けを求めている方も大勢いました。住民の皆さんが助け合っている間を、「消防と連携してすぐに助けにきますから、皆さん続けてくださいね」と声をかけながら歩き続けました。
地震が起きたのが午後4時10分ですから、すぐに暗くなりますし、冬ですから寒い。まずは集まってきた職員と避難所の開設と、食べ物の確保に努めました。でも物資が入ってこないんですね。金沢あたりまでは来ているのでしょうけれど、輪島までは来ない。
能登半島は18年前にも震度6強の地震があったので、その経験を活かして物資を備蓄しておく避難所も決めてました。でも避難所となる建物自体が壊れているような状況です。物量を増やすということもありますが、もっと細かく避難所を設置しておかなければならなかったと反省しています。
そして人命救助ですが、「72時間の壁」がありますから、その間にいかに行方不明者を含めて救助できるか。とにかく情報が入ってこないんですよ。通信がまずダメになりましたから、車で行けるところまで行って、そこからは歩いていかないと、どこにどれだけの人が避難したか、あるいは孤立してるかという情報が取れない。消防と警察は主に救助に当たりましたので、自衛隊の人たちが歩いて一戸一戸を捜索し、どこに何人いるかを確認していきました。
最初は、いかにして孤立集落から脱出させるかということに力を入れました。
—地域によっても違いはあると思いますが、震災に対して共通していえるアドバイスはありますか。
坂口 家屋はもちろんですが、インフラも震度7は想定して耐震化すべきだということです。輪島市では一番高いビルが7階建てで、一棟以外は倒壊したり、新耐震基準で建てられた建物でも傾いたりしました。山間地とか海岸沿いといった地域性や支持地盤までの距離など違いはあると思いますが、耐震の基準自体を見直す必要があると思います。


地震直後(上)と1年後(下)の様子
東京都をはじめとする自治体の支援により 上下水道は予定よりも早く復旧
—避難生活で一番問題となったのはどんなことでしょうか。
坂口 食料や水、衛生用品の不足、プライバシーの確保などいろいろありますが、やはり一番大変だったのが水、特にトイレです。非常時には、水が少しあれば、人は1、2日食べなくてもなんとか我慢できますが、トイレの劣悪な状況には困りました。トイレに行きたくないから、食事を摂らないという悪循環になりかねませんから。携帯トイレとか簡易トイレも含めてしっかり整えなければならないと痛感しました。
—今回の地震では、ずいぶん長い間、水が使えなかった印象があります。
坂口 輪島市も上下水道管がかなりやられたのですが、実は応急的な復旧は最初に想定されていた時期よりも割と早かったんですよ。
東京都を中心とする多くの自治体から、水道関係の方が支援に来てくださったんです。
初めに現場を見た都の職員の方からは、水を通すのはどんなに早くても5月末までかかると言われました。私も孤立した集落にいて、劣悪なトイレの状況をなんとかしないと、と痛感していましたので、なんとか3月末までにお願いしたいと頼んだのですが、無理ですと。
どこがどうダメなのか、どこをどうすればいいのか、毎日のように話をしているうちに、ついに「市長がそこまで言うなら、3月末までにやりましょう」と、都の方が言ってくれたのです。うちの職員が尻込みしているにも拘らず、です。そして東京都からどんどん職員を送ってくれて、昼夜違わず、不眠不休で対応してくださって、おおむねのところは3月いっぱいに水を通せたんですよ。
本格的な復旧はこれからですが、自分のことのようにやっていただき、本当にありがたかったですね。
—小池都知事も昨年、輪島市を視察されていますね。
坂口 視察に来られた時、仮設住宅もご覧になったんですね。すごい数の仮設住宅が単調に並んでいると、若い人でも自分の仮設住宅がわからなくなるという話をしたところ、「じゃあ子どもたちに絵を描いてもらって、それを仮設住宅に貼ったら目印になるし、癒されるんじゃないでしょうか」とご提案いただきました。実際に東京の小学生が描いた絵を送ってくださり、実現したんですよ。こんなことも含め、東京の方には様々なご支援をいただいて、本当に感謝しています。

昨年、小池都知事が輪島市を視察
行政としての立場から 輪島市の発展に関わりたい
—ところで、市長は徳島の大学を卒業して、民間企業に勤めてから輪島市役所に入られたそうですね。行政に興味があったのですか。
坂口 私は3人兄弟で三男なんですね。生まれ故郷である輪島市に戻る気はなくて、民間会社に入ったんですけど、両親が立て続けに体調を悪くして気弱になった。長男は別居、次男も遠く離れていたので、私に戻ってこないかと声がかかったんです。たまたま市役所が技術者を募集していて、じゃあ受けてみるかと(笑)。
行政の仕事に携わるなかで、自分のなかで人生のテーマみたいなことを考えて携わると、より強い気持ちでやってみようと奮起することができましたね。
—どんなテーマですか。
坂口 まちづくりです。輪島市の発展に行政として関わって、その支援をしたい。ソフトの部分も含めて、いい輪島市にしたいと思ったんです。青年会議所に入って、皆さんと一緒に景観条例を作ったり、街並みのファサードを統一したり、空港の建設にも関わりましたし、マリンタウンの開発にも携わりました。
—震災を経た今は、輪島市をどうしていきたいとお考えですか。
坂口 例えば、輪島塗の海外展開と若手人材の育成です。市としても独自の予算を確保して、最低3カ年はしっかりと取り組んでいく所存です。輪島塗の工房も大変な被害を受けましたが、国が100%負担して、スピード感を持って仮設工房を整備してくださり、現在85室の工房で皆さん作業をしています。
輪島塗の関係者によりますと、震災前はインバウンドは2%もなかったのですが、売上は全体の2割ほどあるとのこと。だったらインバウンドを進めるべきですよね。
それで、観光についてはツーリングだろうと。外国の富裕層をターゲットに、コロナ明けから力を入れてやっていたところに地震があった。地盤が隆起したために新たな風景もできてきていますので、震災復興も合わせて、被災地をしっかり回ってもらうインバウンドは推進していこうと思っています。
それから農林水産業。輪島は水産業が盛んなのですが、特に輪島港が隆起して完全に使えなくなってしまいました。これまでも船が縦列になって、人の船を渡ってこないと陸に上がれないといった課題があったのですが、漁業用だけでなく物流の港としても活用できるような、新たな港を作っていこうと考えています。
農業に関しても大きな被害が出ました。トキの餌場となる水田をモデル的に整備して、トキを放鳥することで、米に付加価値をつけていければと思っています。
林業については、生業としてはあまり手をつけていなかったのですが、今回の地震で山腹が崩壊したこと、さらに昨年の台風10号と豪雨により倒木した木々が土砂と一緒に流れたことが、被害を大きくした原因でありますので、治山という意味でも山間の林業はしっかりやらなくてはと思っています。
—こんな大変な時に行政のトップにあることをどう思われますか。
坂口 こういう大変な時期に、こういう立場で、地元輪島市の復旧復興に携われるということは、自分の人生における集大成になる、ここはしっかりやらなければならない、と覚悟を決めました。決して楽ではないし、しんどいです。でも、やりがいはあるし、これまでやりたくてもできなかったことにチャレンジすることもできる。
語弊はあるかもしれませんが、男冥利に尽きる、幸せな人生だと思います。
※2025年4月11日にインタビュー

吹雪の中でも上下水道復旧作業は行われた