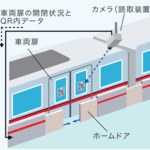チームのために
自分のすべきことをする

株式会社HiRAKU代表取締役 廣瀬俊朗さん 協力/プライベートクラブ「OCA TOKYO」
5歳でラグビーを始め、北野高校、慶応義塾大学、東芝でプレー。2007年には日本代表に選出され、2012年から2年間はキャプテンを務めた。W杯2015ではメンバーとして南アフリカ戦の勝利に貢献、W杯2019では公式アンバサダーとして活躍した。現役引退後は大学院で経営を学び、MBAを取得。現在は株式会社HiRAKU代表取締役としてスポーツ普及、教育や食、国内外の地域との共創プロジェクトなどに取り組んでいる廣瀬俊朗さんにお話を伺った。
スポーツ、音楽、アート…言葉がなくても通じ合えるものを大事にしたい。
—2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップは大いに盛り上がりましたが、大会前に放送されたTVドラマ『ノーサイド・ゲーム』でラグビーに興味を持った人も多かったと思います。廣瀬さんも重要な役で出演されていましたね。
廣瀬 演技の経験はなかったので、緊張もしましたし、怖さもありましたが、終わってみればとてもいい経験をさせてもらったと思っています。自分にとってもそうですが、とても人気があるドラマ枠で放送されたことで、ラグビーを知っていただく機会ができたことが何よりも嬉しかった。それにフィクションならではの近さ、角度の映像だったので迫力があり、ラグビーの面白さがよく伝わったのではないでしょうか。
それから、ミュージシャンの村田匠さん、歌手の田中美里さんと「スクラム・ユニゾン」を結成して、「国歌を歌っておもてなしする」をモットーに、日本代表の試合会場やイベント会場などで世界19ヵ国からやって来る選手やファンをお迎えするという活動をやったんですね。今年4月、代々木体育館で車いすラグビーの「SHIBUYA CUP 2025」が開催されたのですが、オーストラリアとの最終戦の時、オーストラリアの国歌を歌ったらめちゃくちゃ喜んでもらえました。
スポーツもそうですが、音楽とかアートとか、言葉がなくても通じ合えるっていうのかな、そういうものは大事にしていきたいですね。特にコロナ禍では、不要不急ということでそういうことが止まってしまった。自分たちとしては、そういう時こそ国歌の収録を続けることで音楽を止めないという思いはありました。
—それでご自身の会社を設立されたのですか。
廣瀬 ワールドカップを盛り上げたいというのが会社設立のひとつの目的だったので、ワールドカップまで突っ走って、終わってからどう盛り上げていこうかという時にコロナが発生した。リアルな世界で価値を生み出していくことが多かったので、最初はやはり戸惑いましたが、改めてスポーツの価値とか、自分が何をしていきたいのかを見つめ直す機会になったのではないかと思います。
会社の名前は「株式会社HiRAKU」といいます。「ひらく場、ワクワクする場を作りたい」と思って名付けました。例えば、CAFE STAND BLOSSOMでは、甘酒をテーマに「発酵食品」を多くの人に改めて知ってもらいたいという思いから始めたものですし、「スクラム・ユニゾン」は歌を通してみんながつながっていこうというプロジェクトです。
何をやるかよりも、どういう思想でやるのかが大事だと思うので、一見関係ないように見えるかもしれませんが、人とつながる中で、何かがひらいていく、何かもう一つ面白いものを付与できるような、誰もやったことがないことをやっていきたいと思っています。

現役時代はウイング、スタンドオフとして活躍

宮崎の耕作放棄地で行っている米作りプロジェクト
ラグビーは各自が「チームのために」自分の仕事をすることが大事。
—ラグビーを始めたのは5歳の時とか。以来、ラグビー一筋で?
廣瀬 小学生の頃はサッカーとか野球もやっていたんですよ。ただ、大阪はラグビーがとても盛んなエリアで、「チームプレーのスポーツをやらせたい」という親の方針もあって地元のラグビースクールに入りました。そこは鬼ごっこやキックベースといった遊びを通じて、楽しみながらラグビーの基礎を学ぶところで、勝つことのみに注力せず、「みんなで楽しむ」ことが大切な哲学だったので、楽しんでやっているうちに好きになっていったという感じです。
—ラグビーの魅力は那辺にあると?
廣瀬 体が大きい人も小さい人も、そのままの自分で活躍できるポジションがあるとか、考えるのが好きな人もそうでない人もみんな活躍できる、そういう多様性があるところがすごく好きです。それに、格闘技的な要素もあるきついスポーツなのに、チームのために体を張るという美学みたいなところもいいなあと思いますね。
—「ワンフォーオール、オールフォーワン」ですね。
廣瀬 どのスポーツもそうだと思いますが、「チームのために」という思いが特にラグビーは強い気がします。
例えば、野球はすごいピッチャーがいたら、なかなか点が取られないじゃないですか。チームスポーツだけど、1対1の連続みたいな感じがします。でもラグビーは、スクラムも一人じゃ組めないし、ラインアウトも一人ではできない。仲間と一緒にやるシーンがとっても多いんですよ。
—チームをまとめて引っ張っていくキャプテンを、高校、大学、東芝、日本代表でも務めました。キャプテンシーというか、リーダーの素質は小さい頃からあったのですか。
廣瀬 そんなに喋るタイプでもなかったので、一般的に想起されるキャプテンの素質はなかったと思います。高校くらいまでは、ラグビーが上手で後輩の尊敬を得られれば務まるかもしれませんが、社会人、日本代表になるとそれだけではないものが大事になってくるんですね。すごく悩んで、試して、いろんな人にフィードバックしてもらって、ようやくキャプテンになれたという気がします。
—でも、日本代表のヘッドコーチを務めたエディー・ジョーンズ氏に「自分がラグビー界で経験した中で、ナンバーワンのキャプテンだ」と言わしめた。
廣瀬 ラグビーは外国出身の選手もいますが、同じ代表の仲間という感覚で国籍の違いはあまり気にしないんですね。でも、やはり言葉の問題もありますし、文化的な違いはある。キャプテンとしては、まずはお互いを知ることからスタートして、それからバディと呼ばれるメンター制度を作ったり、コミュニケーションを取る機会を増やしたり、とにかくお互いのことを知る機会を作るようにしました。
人と人をまとめるピースの人、歌を歌ってまとめるピースの人、いろんなピースがあって、みんながそれぞれの役割をちゃんと果たした結果、一つの形が完成したと思うんです。僕はたまたまそのキャプテンでというピースだったという感じですね。先ほども言いましたが、みんながチームのために自分の仕事をすることが本当に大事なんですよ。

ケニアでラグビーを指導。国を超えて繋がりをひらいている
グローバルに展開していく可能性にチャレンジしたい。
—日本代表だけでなくいろんな試合に出ていますが、一番印象に残っている試合は?
廣瀬 やはり2015年にイングランドで開催されたワールドカップ、強豪南アフリカを破った試合です。
実は、僕はそのワールドカップの試合には出ていないんです。日本代表には選ばれていたのですが、2014年にリーチマイケルに日本代表のキャプテンを交代してからは試合の出場機会が減っていました。正直辛かったですが、一生懸命頑張っても試合に出られないこともある。それまでの努力を否定するのではなく、そこから何を学んでどう生かしていくかが大事だと思い直し、チームのために自分ができることをしようと決めました。
日本のラグビー界が変わっていく現場に立ち会えたことは誇りに思っていますし、それと同じくらい、素晴らしいチームができたことが、とても嬉しかったですね。
—良いチームとはどういうチームだとお考えですか。
廣瀬 人間関係が良くて、大義があって、オリジナリティを持っていて、努力し続けられるということでしょうか。そもそも日本代表は何のためにあるのか、自分自身はどうありたいのか、何のために頑張るのか。そのチームの存在意義をみんなが共有していることが大切だと思うんですね。
漠然としたビジョンではなく、「みんなが日本代表のジャージを着て試合会場にきてくれる。パブリックビューイングに来てくれる。そういうチームを作りたい。そのために頑張ろう」という絵を明確に、皆で描きました。
その結果、2019年のワールドカップでは全勝で一次リーグを突破して準々決勝に進出。残念ながら南アフリカの厚い壁に阻まれましたが、ベスト8という輝かしい成績を収めることができたんです。
—2015年のワールドカップの翌年、30年間の現役生活にピリオドを打ち、ビジネス・ブレークスルー大学大学院で経営を学んで経営管理修士(MBA)を取得され、2019年のHiRAKU設立に至るわけですね。一番力を入れているのはどんなことですか。
廣瀬 一つは教育です。自分自身のキャプテン経験をキッカケに考える機会をつくりたいと思っています。それからグローバルに展開していく可能性があるものにチャレンジしたいです。
今、日本ラグビーが強くなっていったプロセスを教えてほしいということで、アフリカ・ケニアのラグビー協会およびアカデミーをサポートしているんです。ゆくゆくはケニアの学生が日本の高校や大学でプレイして、卒業後は日本でビジネスをして、それをケニアに持って帰るというようなことにつながると面白いですよね。反対に、アフリカやケニアに行って、ビジネスをしたいという日本の企業も出てくると思うんです。その時の橋渡しみたいなこともやっていきたいです。
食糧問題にしても何にしてもそうですが、どの国も自国だけでは生きていけません。日本の将来を考えた時、今まで以上に日本のプレゼンスを示していく必要があると思います。そのためにも、挑戦する人が増えて、たとえ失敗したとしても再挑戦できるような社会になっていくことが重要です。これからも世界との交流を生み出すようなことにチャレンジしたい、しないといけないと思っています。