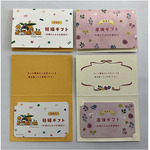多様な人がいる。それが当たり前な社会。

日本財団職員 東京2025デフリンピック応援アンバサダー 川俣 郁美さん
3歳の時、高熱によりろうに。将来について悩んでいた高校時代、偶然目にしたドキュメンタリーが人生を変えた。アメリカの大学に留学し、障害者支援の道へ。日本財団でアジア地域にろうの子どものための学校を開設する事業に従事しつつ、東京2025デフリンピックの応援アンバサダーとして尽力している川俣郁美さんにお話を伺った。
デフスポーツには、視覚的に情報を得る、音に頼らない工夫がいろいろある。
—開催まで100日を切ったデフリンピックについて簡単にご説明いただけますか。
川俣 まず、デフリンピックという言葉ですが、「デフ」は英語の「ろう者・難聴者」の意味で、聞こえない人たちのことです。「リンピック」は、皆さんご存知の「オリンピック」。その2つを組み合わせた言葉です。国際的なろう者・難聴者のためのスポーツ大会で、おおむね4年に1回、夏季、冬季開かれています。
初めて開かれたのは1924年、今回は100年記念の大会になります。日本で開催されるのは今回が初めてのことで、とても嬉しく思っています。70〜80の国と地域から選手3000人、スタッフ3000人くらいが集まると予想されていて、応援や観戦に来る人たちを合わせると、本当に多くのろう者・難聴者が世界中から集まることが期待されているんです。
—すごい規模ですね。迎え入れる側の心構えや、やっておくべきことは何かありますか。
川俣 ろう者・難聴者は、補聴器や人工内耳を使っている人もいますが、何も使ってない人もいます。あるいは髪の毛で補聴器等が見えない人もいるので、車いすの方や白杖を使っている障害者の方と比べると、外見からはすぐにろう者・難聴者と分からないことが多いです。
このデフリンピックの期間中、その前後も合わせてですけれども、世界中から多くの聞こえない人たちが集まります。
例えば見た目が外国人で、英語なら通じるかなと話しかけても通じないことがあるかもしれません。そういう時は、もしかしたらろう者かもと思って、指差しをしてみるとか、身振りを使ってみるとか、少し手話を覚えて使ってみるとか、聞こえない人もいるということを頭に入れて、コミュニケーションをとっていただければと思います。
今回のデフリンピックは観戦が無料ですので、ぜひ見に行って、デフとは何なのか、デフスポーツはどんなものなのかを知って、理解を深めていただきたいです。きっとかけがえのない体験になると思います。
—これは覚えておいたほうがいいとか、こういうところを見ると面白いとか、デフスポーツを楽しむポイントを教えいただけますか。
川俣 21種類の競技があるのですが、基本的には聴者のルールに準じています。
けれども、音を使う部分に関して、例えば陸上や水泳はスタート時にピストルの音を使いますが、代わりにライトを使います。あるいはサッカーはホイッスルを使いますが、これは旗を使う。また空手では審判が「止め」と言葉をかけますが、「止め」の声と同時にライトが光るようになっているんです。
また、バレーボールのように、審判がネットを揺らすこともあります。それを見ると、選手は「あ、呼ばれている」ということが分かります。視覚的に情報を得る、音に頼らない工夫がいろいろあるんですよ。
—聞こえる人にとっても分かりやすいかもしれませんね。
川俣 私たちろう者だけでなく、障害のある人にとって分かりやすかったり、便利であることが、実は障害のない人にとっても役に立つことがたくさんある。とても嬉しいことだと思います。

中野区立桃花小学校でデフリンピック出前授業を行う ©東京都

日本財団が助成しているラオスのバイリンガルろう学校で、手話で授業を受ける生徒たち
たとえ聞こえなくても 諦める必要はない。
—川俣さんがろうになったのは、幼い頃の高熱が原因だそうですね。
川俣 3歳の時、はしか、おたふくと連続でかかって、高熱が続いたんです。その後、熱は下がったのですが、親が呼びかけても反応がなく、これはおかしいと病院で診てもらったところ、ろうになっていることが分かりました。
—ろうになって苦労したり、悩んだことは?
川俣 小学校は聞こえる子どもたちと同じ学校に通っていたので、ろう者は私だけという環境の中で学びました。低学年の頃は、たとえば友だちと喧嘩になって、言った言ってないみたいなやり取りありますよね。そんな時に、相手は言ったけど、実は私は聞こえていなかったということを周りの方が気づいてくれることもありました。
自分自身が聞こえないと本当に認識したのは高学年になってからです。例えば音楽の授業の時に歌を歌うと、みんなからチラチラ見られるんです。何だろうと思うと、「声が変だよ」と言われたり、あるいはグループワークの時にディスカッションがありますね。私は何が話されているか分からないので、会話に入れないという状況がありました。
補聴器を使い始めたのは小学3年生からなのですが、先生から「つけなさい」と言われて、そういうことから違いに気づき始めてはいたのですが、中学に入るとやはり強く意識するようになりましたね。中学は難聴学級がある学校に通っていたのですが、補聴器を髪の毛で隠して見えないようにしていました。
—今の川俣さんはすごく明るく楽しそうですが、そんな意識が変わったきっかけは何だったのでしょう。
川俣 ひとつは高校受験です。私は公立の高校を受験してそこに入ったのですが、公立を受ける前に私立も受験したんです。一緒に受けた仲の良い友だちは合格したのですが、私は不合格。その友だちに「郁美のほうがいつもテストで上なのに、落ちるなんておかしい」と言われて、「どうしてだろう」と先生に聞いてみたんです。
すると、「あの学校は聞こえない学生を受け入れられないから、断られたんだ」と。すごくショックを受けました。
その頃は障害者差別解消法のような法律はなく、障害条件を理由に断るということがあったんですね。でも、両親が怒ってくれた。教育委員会に交渉したり、いろんなところに働きかけてくれて、半年後にその不合格を取り消してもらったんですよ。当時はその時のことは思い出したくない、忘れたい思い出だったのですが、「たとえ聞こえなくても、諦める必要はないんだ」ということを気づかせてくれました。その時の両親の行動には今も感謝しています。

2008年ギャロデット大学留学1年目、クラスメイトと
ろう者でも大丈夫!豊かな人生が待っていると伝えたい。
—アメリカの大学に留学したのはなぜですか。
川俣 発展途上国のガーナのドキュメンタリー番組を見たのがきっかけです。ある兄弟がいて、2人とも本来であれば学校に通う年齢なんですね。でも父親がいなくて、母親が病気で伏せている。子どもたちが生活のために働かなくてはいけないという内容でした。
その時、私は高校生で、聞こえる子どもたちに囲まれて学んでいる時で、授業にもついていけず、何のために学校に行っているのかと悩んでいたんです。そのドキュメンタリーを見て、学校は学問を学ぶだけではなくて、友情を深めたり、社会性を身につける大事な場であるということに改めて気づかされました。
日本では、私たちは当たり前のように学校に行くことができているのに、テレビの中では学校に行きたいのに行けない子どもがる。聞こえる子どもでも学校に行けてないとしたら、ろうの子どもはどうしているんだろうと、開発支援に興味が湧きました。それでアメリカのギャロデット大学に留学することにしたのですが、ものすごく貴重な体験でした。
—どんな大学なのですか。
川俣 もともとろう者・難聴者のために作られた手話で学べる総合大学ですが、聴者も入ることができます。例えば将来、手話を使った仕事をしたいとか、ろう者の子どもに関わる仕事をしたいとか、そういう聴者ですね。でも、多数がろう者なので、聞こえる人はマイノリティです。
そこにはろう者がたくさんいて、そのことに誇りを持って生活しているんです。まず学長がろう者ですし、社長とか学校の先生、医者、弁護士になっている人もいる。本当にいろんなロールモデルのろう者がいて、そういう人に会うことができます。このコミュニティの中でろう文化が受け継がれており、ろうでいいんだ、ろうだからこその魅力、面白い世界があるんだということに気づくことができました。
そこでいろんな方に出会う中で、将来は特にアジア地域の子どもたちが手話で学べる学校を作りたい、その支援をしたいという夢をいただくようになりました。日本は先進国ではありますが、障害関係についてはまだ課題が多くとても先進国とは言えません。だからこそ、日本財団に入り、今、国際開発の仕事をしながら、プライベートでは国内のろう者支援にも関わることができていてとても嬉しく思っています。
—最後にこれからやりたいこと、伝えたいことがあれば。
川俣 まずは、デフリンピックを成功させたいです。小学校に行って手話とは何かとか、デフリンピックとはみたいな授業をさせていただいたり、イベントに出向いたりと、アンバサダーとしてPRを頑張っているところです。
それから、いろいろなところに多様な人がいる。それが当たり前という社会に変わってほしいと思っています。ろう者・難聴者だけでなく、障害者を見るとかわいそうとか、大変だろうなというイメージを持つ人が多いと思いますが、実際は違います。例えば手話があれば、そこにはまた別の世界があって、別の知識、別の価値観に出会うことができる。そこには聴者とはまた違うすっごく面白い世界が広がっているんです。
ろう者でも大丈夫だよ、一人ひとり、その人にしかない豊かな人生が待ってるよ、ということを、ろう・難聴の子どもたち、その家族、皆さんに伝えていきたいと思っています。